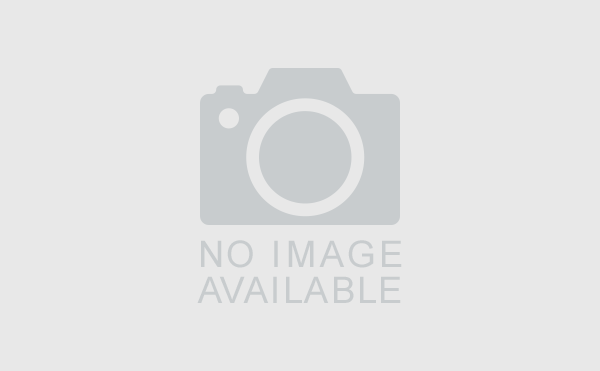税制への対処
税制度は国の基本ですが、同時に国の正義と民の正義が真正面から衝突します
大日本租税志第一冊土地制度(大正15年12月11日に初版が発刊)の「序文」に「租税は一國の政治の枢軸なり。青史を繙くに洋の東西を問わず、時の古今を論ぜず、善政は,正しき税制と相伴い、苛税は紛淆せる政治と相表裏す。両者互いに因果を為して、或いは国家を興隆の楽園に導き、或いは之をして亡國に悲淵に沈ましむ。かるが故に一國の要諦、延べきて国民生活安定の基調は正しき税制の確立にあり・・・」とあります。
格調の高い文書であり、なるほどなあと思います。この序文を書いたのは当時の大蔵大臣官房文書課長青木得三氏です。しかし国民の側からは正しき税制などはありません。租税の正義は国家の手の内にあるものです。
現在の消費税などは仮に赤字経営であっても納めねばなりませんから、納税者の側に立てば、これは罰金ではないかと思うこともあります。現在日本の直接税には法人税・所得税・相続税があります。これらの税をどのように少なく納めるかということは、全体最適の中で考えることになります。
租税の歴史と国民の対応(ただし脱税は結局損をしますよ)
租税制度も歴史のなかで観察すれば、驚くほどの変化が見られます。
現在の法人税が創設されたのは昭和12年です。この年に所得税も大きな改正をしており、所得の性質から、不動産所得・配当利子所得・事業所得・勤労所得・山林所得・退職所得の6種類に分類され、戦費調達の必要から増大が計られたのです。このときに勤労所得に対して源泉徴収課税の方式が採用されました。明治3年には国税であった地租税・営業税・家屋税が地方税となり、現在に至っています。営業税は現在の事業税です。
我が国の税制の淵源は、神武天皇の頃に祖(たちから)・役(えたち)調(みつぎ)に始まります。今はいかなる税も現金での納付が一般的です。大昔、祖はお米、役は労役、調は穀物以外の物品その他の雑税でした。
この時代も当然のごとく脱税はあり、それは戸籍の偽りであり。死亡者を生存者のごとく偽り口分田を多く貪るなどの方法があったようです。税制も社会構造の変遷に連れて大きく変わります。今ある税制が未来永劫に続くことなどあり得ません。
人が社会をつくり統治機構を必要とする以上、会費としての税は必要なものです。反面それは収奪としての意味もあります。税への正しい対処の仕方は、現在であれば法人税・所得税・相続税と贈与税などの内容に知悉し、その組み合わせのなかで、目先の税の節税を考えるのではなく、いつどの税法をどの角度から使うのか考えることが、一番の節税方法になります。企業経営であれば、その業績と社会的使命である永続性をしっかり考察し、将来への資金を蓄えながら、税制にも対処するということです。経営者のなかには、税金を納めるぐらいなら、使えばいいだろう、という意見をお持ちの方も散見されますが、賛成できません。