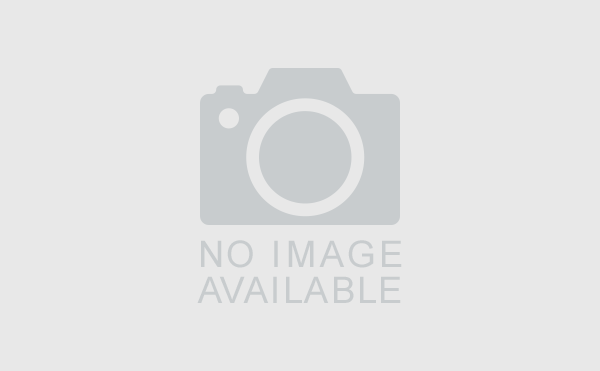企業の成功の物語
~上町会計倉矢事務所は会社が強くなるための応援をしています~
プロローグ
江戸の昔、1人の男が炭屋を始めました。やがて炭だけでなく炭の粉を練り混ぜ成形をした練炭を売るようになり、更に明治時代には石炭を材料にした豆炭の製造にも手を染めるようになりました。
令和の今、創業から180年を経過して、リチウムイオン電池を扱い、水素エネルギ―の研究もしています。創業当時の炭は、今や影もカタチもありません。
現在の当主は創業から数えて9代目です。
事業目的の定義を炭屋から燃料屋としたことで命を得たのです。自らの事業をどう定義づけるかということです。炭だけにこだわっていたら、今日はなかったことでしょう。
大事な話のもう一つは後継者を得るということです。
事業の柱をどのように定義して継続させるのか、更にはその後継者をどのように得ていくのかは一大事。その場合、日本という国の容・風土も併せて視野に入れて検討しなければなりません。
1トップの父性その権威と構成員(社員)の連帯と(企業の構成要素)
組織は人が創るものであり、創業に始まります。経営トップに求められるのは父性と権威です。また構成員の連帯が求められます。この三要素がしっかりと保持できなければ会社は潰れます。リーダーシップについては多くの本が出ています。トップの父性と権威について触れた本はありません。もちろん事業の柱となる製品や商品ないしはサービスが必要なことは言うまでもありません。
例えば、日本の大手自動車メーカーでしっかり生き残っているところの後継者は父性と権威をしっかり引き継いでいます。
後継者は創業家から出ることが、望ましいのです。問われているのは父性であり、そこから出てる威厳と権威が大事なのです。我が日本国を例にしましょう。国から賓客が来たとします。その応接にふさわしいのは、天皇陛下でしょうか、時の総理大臣でしょうか。いうまでもないですね。
仕事ができる優秀な社員を後継者に指名したとします。上手く行けばいいのですが、社員間の渦巻く嫉妬の感情で企業が破壊する場合が多いのです。創業家以外から後継者がる場合は、よほどしっかりとした経営方針書(経営理念といってもいいです)を作り、これを遵守するような経営風土をつくらねばなりません。また日本という風土の中で、永年にわたり伝承されてきた、習慣・秩序の尊重が問われるべきはいうまでもありません。それは言葉を変えれば秩序と連帯の礎ということです。
2経営計画・利益計画から会計への融合ということ
社長は事業を発展させたいし、毎期の利益は次期以降の投資資金として使いたい。ところが国は、税金として収奪します。折角苦労して残したお金が取られてしまうのです。社長にすれば今期の利益は将来の投資資金です。税として収奪されるのは腹が立ちますね。
税務署は怖い、揉めたくはない、ペナルティを取られるのも嫌、自らの品位も落としたくない、税理士も納めよと言うからしょうがないなあ、というのが実感でしょう。経営計画書、利益計画書を作成し、税金も当然視野に入れた上、精密な経営観察の道具としての決算書を作らねばなりません。経営計画や利益計画があり、その結果としての貸借対照表と損益計算書があります。これらをシッカリと作る会社が生き残ります。
3目的としての経営計画書(行くべき方向であり、帰るべき場所が経営計画書)
経営計画書は会社の憲法です。国であれば国境を護り、治安を守り、国民の福利を謳うのが憲法です。経営計画書には、その会社の社会的な意義と向かうべき方向性を書きます。それを大書して社内に張り出して、社員の理解と協力を得るようにします。経営計画書があれば、社員さんも会社の存在意義を感じますから動きやすくなり、協力が得られます。
4目標としての利益計画書(追いかけるのは利益であり 売上ではありません)
経営目的を謳うのが経営計計画書とすれば、利益計画書はそれを達成するための手段(目標)です。ウクライナを例にとれば、ロシアとの和平が成立した暁には、今度は戦争の後始末、治安の復興、国内インフラの整備などを計画しなければなりません。
経営環境は絶えず変わります。1~2年程度の期間で見直しを行います。当初設定した目標値と達成した実績値の差を読み、その原因を分析して、次の利益計画書を作成します。幹部社員・中堅社員は勿論ですが、老長けたパートさん辺りに意見を求めれば、素直で辛辣で新鮮、おや?と思うような回答があるかも知れません。パートさんの意見がいいのは、経営に携わることがなく、自由な目線で会社を見ているからです。
あんちょくに、過去の数字を数%嵩上げしたような利益計画書の作成を税理士に依頼し、それをそのまま銀行に出すなどいうのは、やってはいけないことで、社長自らが十分時間をとって作成すべきものです。また予算書を作成し、管理者を置いて執行管理をしてもらうのもいいことです。そのときに助言者として税理士を使うのはいいでしょう。
5経営計画書の内容
- 利益計画書の意味
利益計画書は、数値を机上で捏ねて整合性を保つことではありません。客筋の目線で、売れ筋商品を研究開発して数値化するという即物的なものです。例えばA社はここが伸びそうだから、こういう提案をしょう。あるいは受注製品であれば、ここをこのように改善すれば、喜ばれるのではないか、というような工夫して数値化したものが利益計画書です。
儲かっている会社は高付加価値高い製品や、商品の開発しているものです。まずコストを考えずまず完璧な商製品を開発します。売値に合わせて、変動費すら吸収できないようなコストをギリギリまで下げた商品の販売を利益計画の対象とするようでは、最初から勝負に負けています。
- 経営計画書には何か一つ目標値を入れよう
利益計画書や会計帳簿を作成する上で、具体的な目標を一つ決めれば、良いのです。
人は目標が定めれば、それに向かって工夫や努力をする生き物です。例えばその会計年度のROE(自己資本利益率)を10%にするというようなことを、利益計画書で書けばいいと思います。現在の自己資本1、000万円として10%なら100万円。次の年は1,100万円の10%ですから、110万円となり、自然と目標値が上がっていきますし、それをすることで、他の勘定科目残高の調整につながります。
もっと単純に、毎年預金を増やすということでもいいと思います。これなら預金通帳を眺めているだけでよいことになります。顧問税理士としても協力がしやすくなります。
⓷経営計画書を活かす
利益計画書が出来たら、社長が先頭に立って販売をしなければなりません。
また利益計画はその進捗状態を定期的にチエックし修正しなければなりません。そのチエックは経営の視点から社長自身が行い、修正は社員と共にします。 海の潮は沖の彼方から満ちてくるように見えて、実は足元から満ちてきます。
先ず一歩 ⇒そして一歩 ⇒更に一歩!!
経営計画・利益計画は正しい会計帳簿とともに事業の存続を実現し、倒産を遠ざけることで、計り知れない富を与えてくれます。
6会計との融合(経営計画書から出発、利益計画書を基に活動し、財務諸表の数値は会社観察の道具として) ~比較可能な正しい会計帳簿作成の指示をするのは社長の役割~。
- 会計帳簿の役割
記帳の義務と正確な貸借対照表及び損益計算書の作成は、社長自身が経営内容を正しく理解するための、社長自身への報告書です。それは資本の浪費を防ぎ、経営の進化を計り、他人へ損害を与えることを避ければ、社会と債権者から信頼を勝ち得ます。
会計は会計ルールに従い、各勘定科目を整理整頓して各期の数値を比較可能ならしめることです。毎月ごとの試算表上で、手許現金などが帳簿残高と合っていないのは論外です。毎月の試算表には必ず目を通すようにしましょう。
会計ルールを尊重した精密で秩序正しい会計帳簿の作成は、一義的には社長への通信簿です。税務署のためではありません。経営状態を経営者自らが適時に把握することは、自社の弱点を観察・発見して業績悪化を予防し、経営者自らの意識を改善し、秩序を質し、経営感覚を鍛えます。
赤字が継続しても -赤字の程度にもよりますが- 資金繰りが確かなら、会社は潰れません。
どんなに経営が苦しくとも、融資目的で誤魔化しの決算書の作成を指示すれば、社長に奇妙な安堵感が広がり、藁にもすがりたい状況下では、自分自身に間違った暗示をかけることになり、更なる油断が生じます。
- IT技術の進化であんちょくで、簡単に数値の集計ができるようになった
IT技術の進化で殆ど人の認識を経ないままでの、会計処理が可能となってきています。
数字のおかしさに思いが届かない、誤りに誰も気がつかない。あるいは、もうすぐ複式簿記会計の構造や効能、意味が分からない会計担当者、企業が出てくるかも知れません。ITが進化したときの一番に危険性はここにあります。気をつけましょう。
7事業の質の決め手は人、現場力を高めること
良い商品や製品を社会に提供することで、顧客の役に立ち、喜ばれなければなりません。それがなければ、結局事業の継続は出来なくなりますし、先に書いた経営計画・利益計画などもただの砂上の楼閣になります。
一番大事なのは、良い人材を得、会社、経営者、社員の相互信頼であり、質の高い商品力、製品力、価額帯であり、待たせないで提供できるスピードです。
そのためには、常日頃から自社の従業員とのコミュニケーションをよくしておき、その忠言をよく聞くことです。労使の対立があり、その中でコンサルを入れても失敗します。
商品や製品の開発・改善も然りです。
8整理整頓の徹底
環境を整えましょう。在庫・機械・工具・備品・消耗品・ノート・帳簿などが整理整頓され定位置に置かれると、心が整います。それにより無駄に探し回る時間が節約されます。仕事がやりやすくなります。現場力が高まります。また心が整うと積極心が出てきて美醜の理解できるようになります。商品や製品の良さ、悪さに気が付くようになり、余計な物を買わなくなります。その積極心が営業・ものづくり・全ての改善に向かうようになります。
社長はまず、自分の車、机の上やひきだしの中の整理整頓を行うようにしましょう。
9日本の風土を考え、その上に立脚した会社風土を創ろう
例えばピーター・ドラッカーを読めばなるほどと思いますし、参考にもなります。しかしやる気のエンジンにはならないものです。
- 良い人材を得るために ー荻生徂徠―
次の7項目は荻生徂徠の言葉(良い人材を得るために)を現在風に直したものです
- 人の長所は用いて始めて現れるものです。性急に最初からその長所を求めてはいけません
- 人は長所のみ取ればよく、短所を知る必要な有りません
- 社長の好みに合う者のみを用いてはいけません
- 事を大切に扱う人であれば、小さな間違いを咎める必要はありません
- 人に任せるときは、その任せる内容を十分に説明した上で任せましょう
- 上に立つ者は、下の者と才知を争わないようにしましょう
⓻ 人は必ず一癖あります。機材であるが故に、癖を強制して直すとその人の良さ
も無くなります
―やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ(山本五十六)-
- 聖徳太子17条憲法
聖徳太子の17条憲法は日本人の歴史に培われた風俗習慣に馴染んだもので、日常の人間関係の安定剤です。昨今の政治風土も含めた日本社会の実情は、殺伐としております。17条憲法は日本人の社会規範であり、心性に馴染んでいて、識らず潤滑油のような役割を担います。経営において活かして使えば、会社内部における融和と協調の改善に作用するものと思い、ここで取り上げました。
聖徳太子の17条憲法に見る平等感と下の者への接し方 -17条憲法を要約して書くと次のようなことになります。-
《17条憲法の要約》
上に立つ者は、やさしい態度物腰(和の心)で、下の者に接し、決して争ってはいけません。管理職、中間管理職などは礼を持って下の者と接しましょう。問われるべきは信頼の構築です。心に怒りを覚えるようではいけませんし、顔に出る怒りは捨てましょう。また賞と罰は必ず出すようにしましょう。それで、会社が社員に期待することや、方針を弁えて貰うことができます。独断もいけません、大事なことは一人で決めるのではなく、必ず下の者の意見を多く聴取して、間違いの無い判断をするようにしましょう。幹部社員はお互いの職務・職責・職種を理解しあいましょう。それゆえ、上に立つ者は会社に持ち込む私物を派手にしないで、学歴なども誇ることなく、私情は表に出さないようにしましょう。
面白いなあと思うのは、14条に嫉妬あるなかれ、と書いてあることです。実はマキャベリも韓非子も嫉妬の害を説いています。会社の上層部が嫉妬に狂いだすと会社はおかしくなります。嫉妬はいけません。嫉妬は組織を破壊します。内部管理において経営者が気を配るべき事柄です。
10人を使うコツ
会社への忠誠心を持ってもらうこと、そのために必要なのは給料だけではありません。
アメリカと戦った日本兵はなぜ、かくも強かったのか。それは郷土愛に溢れていたからです。また一度でも社員を侮辱するようなことをすれば、重要な場面での働きは期待できません。人心を把握する上で、厳格主義と温情主義はどちらがいいのか、それは指揮官の性格を反映したものになるで、どちらがいいというものでもありません。大事なことは憎しみを買わぬようにすることです。
先に荻生徂徠の心得や聖徳太子の17条憲法を上げたかと言えば、そのなかに日本人の心性が表れていて、人の深層心理に訴えて識らず共感・協調を得るツールだと思うからです。
11コンサルタントの指導や経営指南書は、殆どの場合あまり役には立たない
私の手元に「申し訳ない、御社を潰したのは私です。~コンサルはこうして組織をぐちゃぐちゃにする~カレン・フェラン著 神崎朗子訳」という本があります。
コンサルを入れたとします。大方は失敗をします。コンサルは自らの経験・知見により短期で効果を出そうとします。現場の共感を得られず、押し付けになってしまい、やる気のエンジンには点火しません。本当は現場の話を聞き、協力を得なければならないのにそれを飛ばしてしまうことが多いのです。どのように会社を運営し業績を上げていくかはその時々の経営環境を観ながらの経営トップの考え方・判断・熟慮ということになります。
コンサルの役割は、まず社長が学ぶということ、それを社長が自社に合わせて翻訳し、あるいは社長の意向をコンサルに伝えて、社員さんに対しては、社長の代弁者になってもらうというのが、正しい方法です。